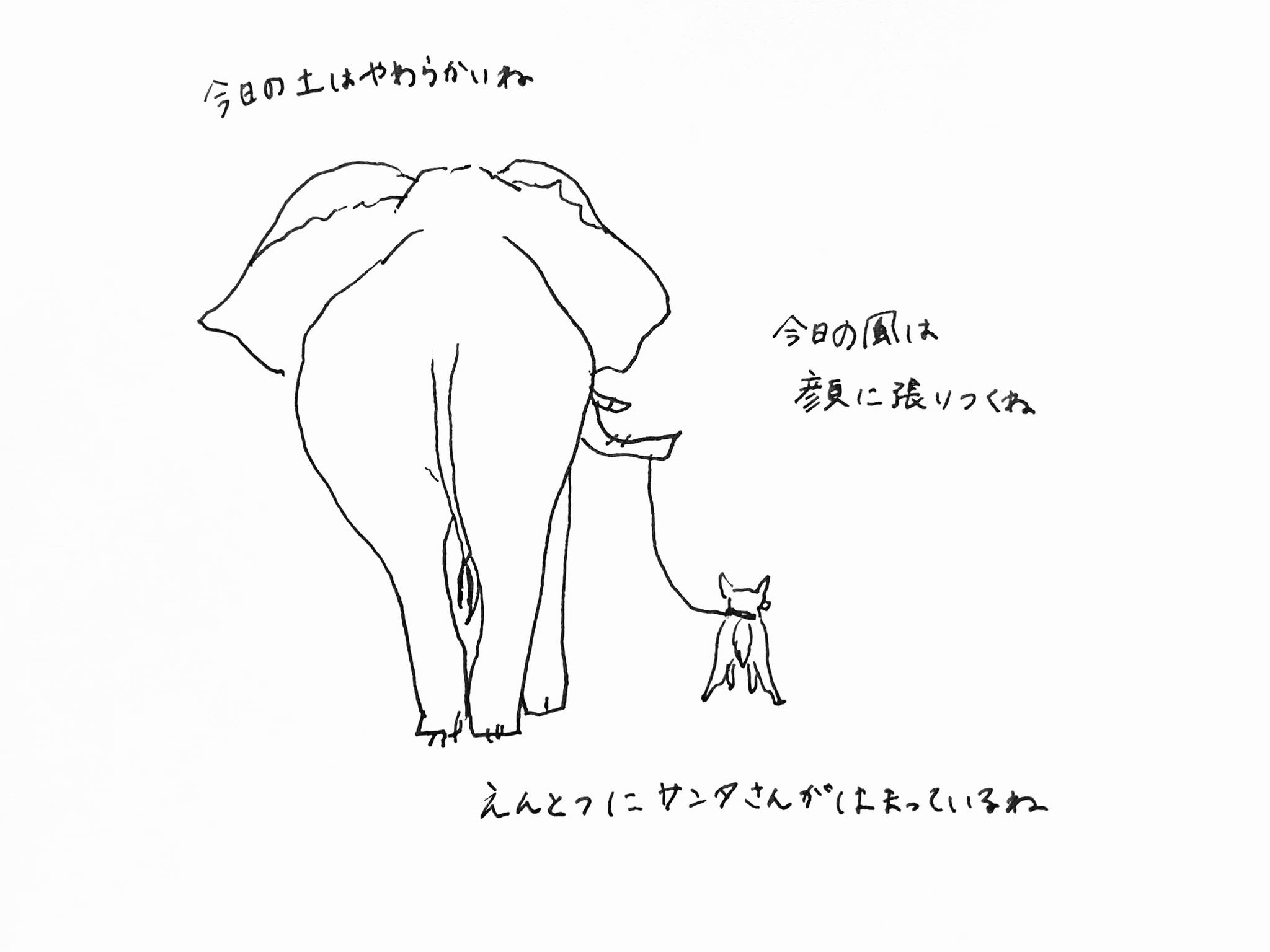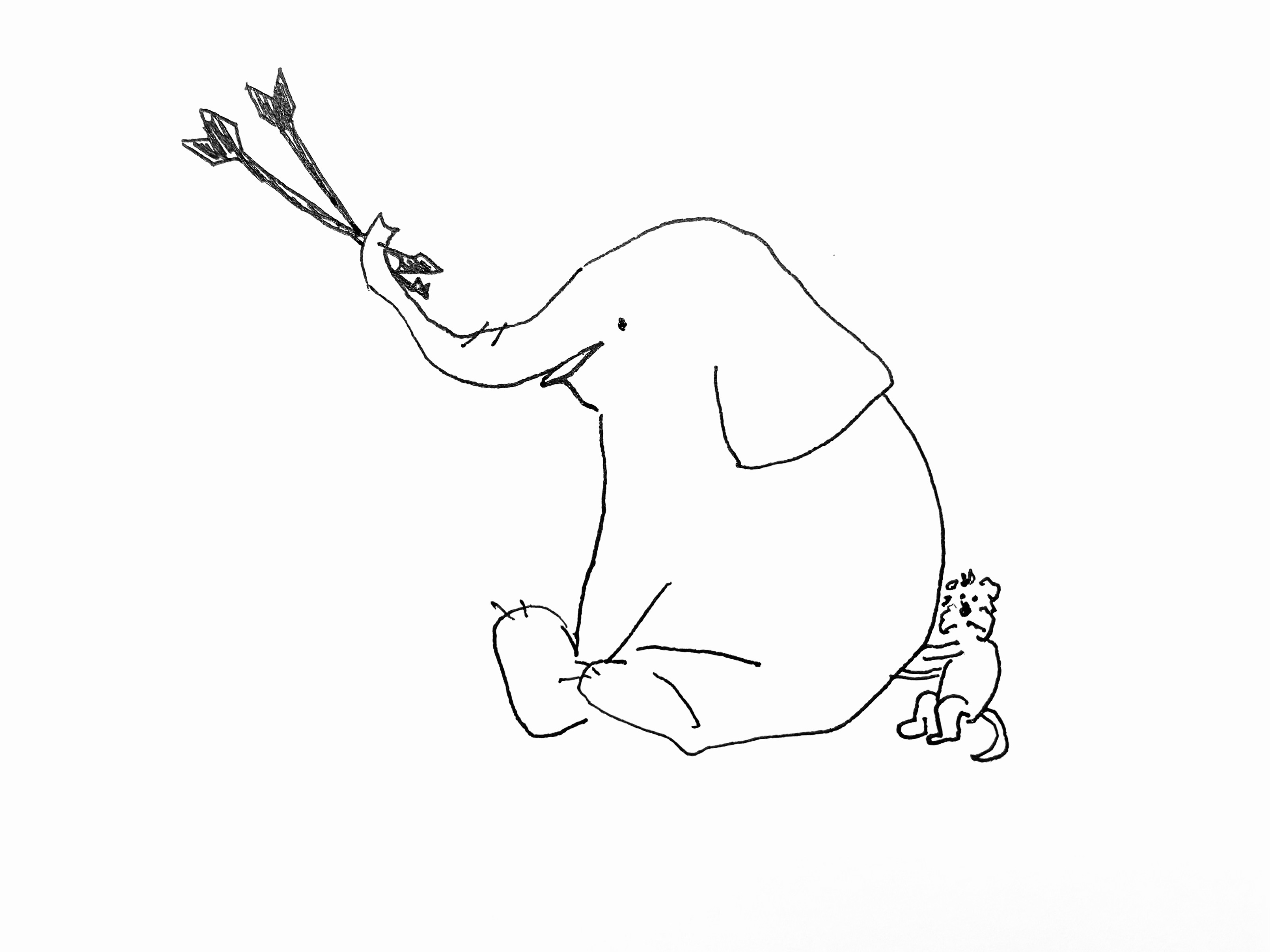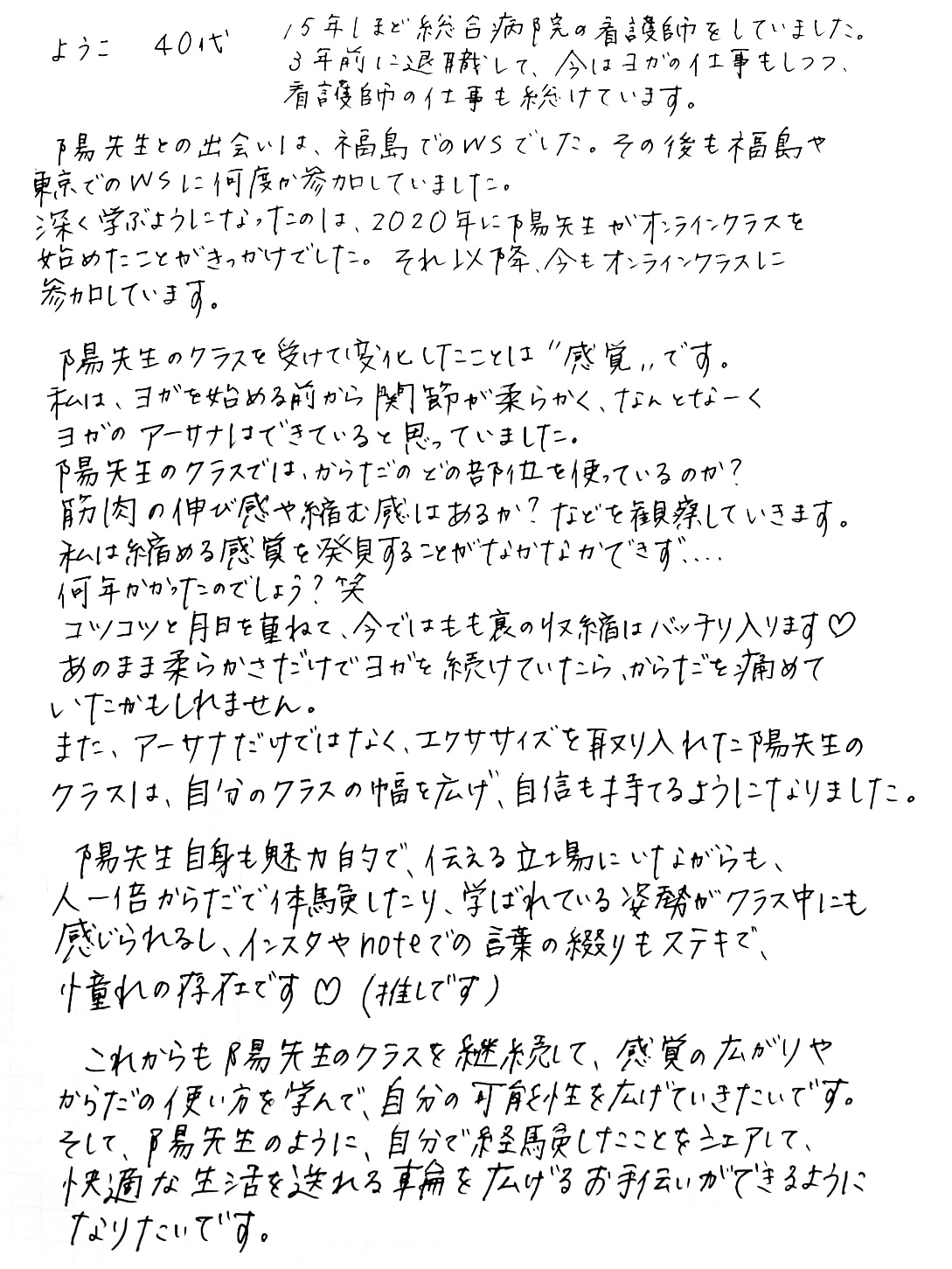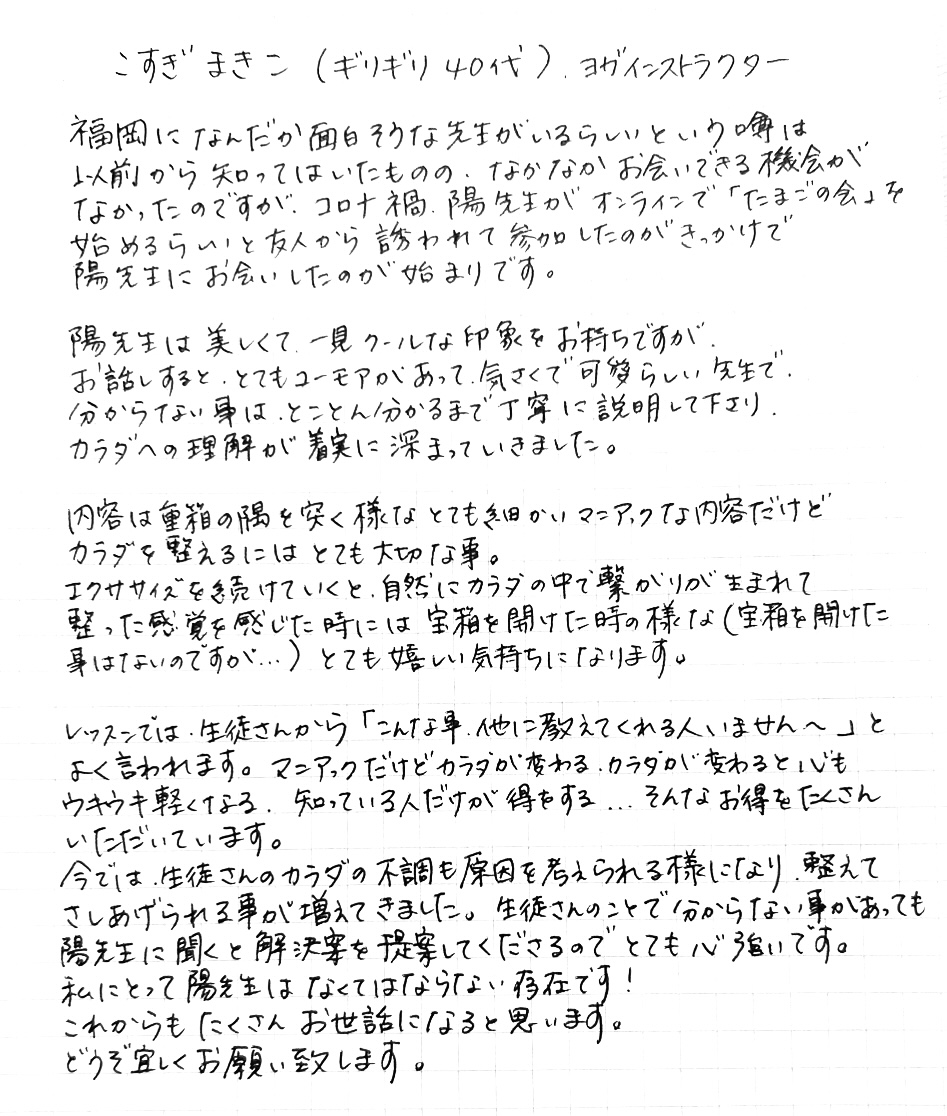書家の娘として育つこと
「ようちゃんは墨のにおいがする」
と幼い頃よく友達に言われていて、私には自分が墨のにおいがする事が分かりませんでした。
私は書家の家に生まれました。
祖父が「福岡書芸院」という名の会を作り、父へと、そして祖父と父が亡き今は姉が継いでいます。
書家の家だというと、厳格な家に育ったイメージを持たれたり、「家でお父さんは着物を着ているの?」としばしば聞かれる事もありました。
我が家に関しては全くそういうことはなくて、父に「書を継ぎなさい」など言われた事もありませんでした。洋服に関しても、父は家でもいつでもお出かけできる格好で過ごすことをモットーとしていたので、若い頃は白かチェックのシャツにデニム、晩年も冬には黒やネイビーのカシミアのニットにコーデュロイのパンツという感じでした。私の姉は墨がつくからと、黒い服をよく選んでいます。
書があることが当たり前で、書を書くことに抵抗がないというのが、もしかしたら特有の感覚なのかもしれません。
書は下手だから書けないと言われることもよくあるのですが、
我が家のリビングには
「絵でも書でも上手に書こうだなんてとんでもないことだ」
という熊谷守一の言葉を彫った父の版画が飾ってあり、毎日それを見て育ったので、書に対する初期設定がそもそも違ったように思います。
以前インドで緑化活動をしている友人に仕事についての話を聞いた時にとても感銘を受け、一つのことに長く時間をかけてきた人達に話を聞いてみたいと思い、父にも書について聞いた事がありました。
1:みんなに褒められる一般的に上手と言われる字を書けるようになる秘訣は?
先生の言うことを聞いて、お手本を真似て、そっくりに書けるようになるまでたくさん書くこと。
2:自分の字で、自分の作品を作る秘訣は?
筆で日記を書いたり、思いついたことを書き留める。(鉛筆でもよい)。
誰かの言葉でなく、自分の言葉で書くことが、自分の作品になる。
3:豊かな字を書く秘訣は?
豊かな書に出会うこと。
豊かな書をたくさん見て、たくさん書く。
たくさんとはどのくらいかというと、父は大学卒業してから30歳になるまで、毎日夜中から明け方まで臨書していたそうです。臨書とは古典の原本をしっかり見て、線を観察しながら書く事です。何を書くかによって枚数は変わるけれども、1日半紙に30〜60枚、1年間で1万枚以上。30歳になった頃に「もう人の真似をするのはやめよう」と思い、臨書するのをやめたそうです。父が大好きだった坂口恭平さんも常に質より量と言われていますが、この量をこなせる人というのが一握りではないでしょうか。
祖父も父も亡くなる直前まで現役で仕事をしていましたし、毎日本を読み、書の探求を続けていました。私も「なぜそんなにずっと体の勉強を続けられるのか」と聞かれたり、「とても努力家だ」と言われることがあるのですが、自分としてはあまり努力している感覚はなく、父の学び続ける姿を見て育ったのでそれが当たり前だからなのかもしれません。
自分が墨のにおいがすることが分からないのと同じくらい、私という人間は隅々まで父の影響を受けていたようです。でも嫌いじゃない。
おじいちゃん、おとうさん、そして姉よ、継いでくれてありがとう。