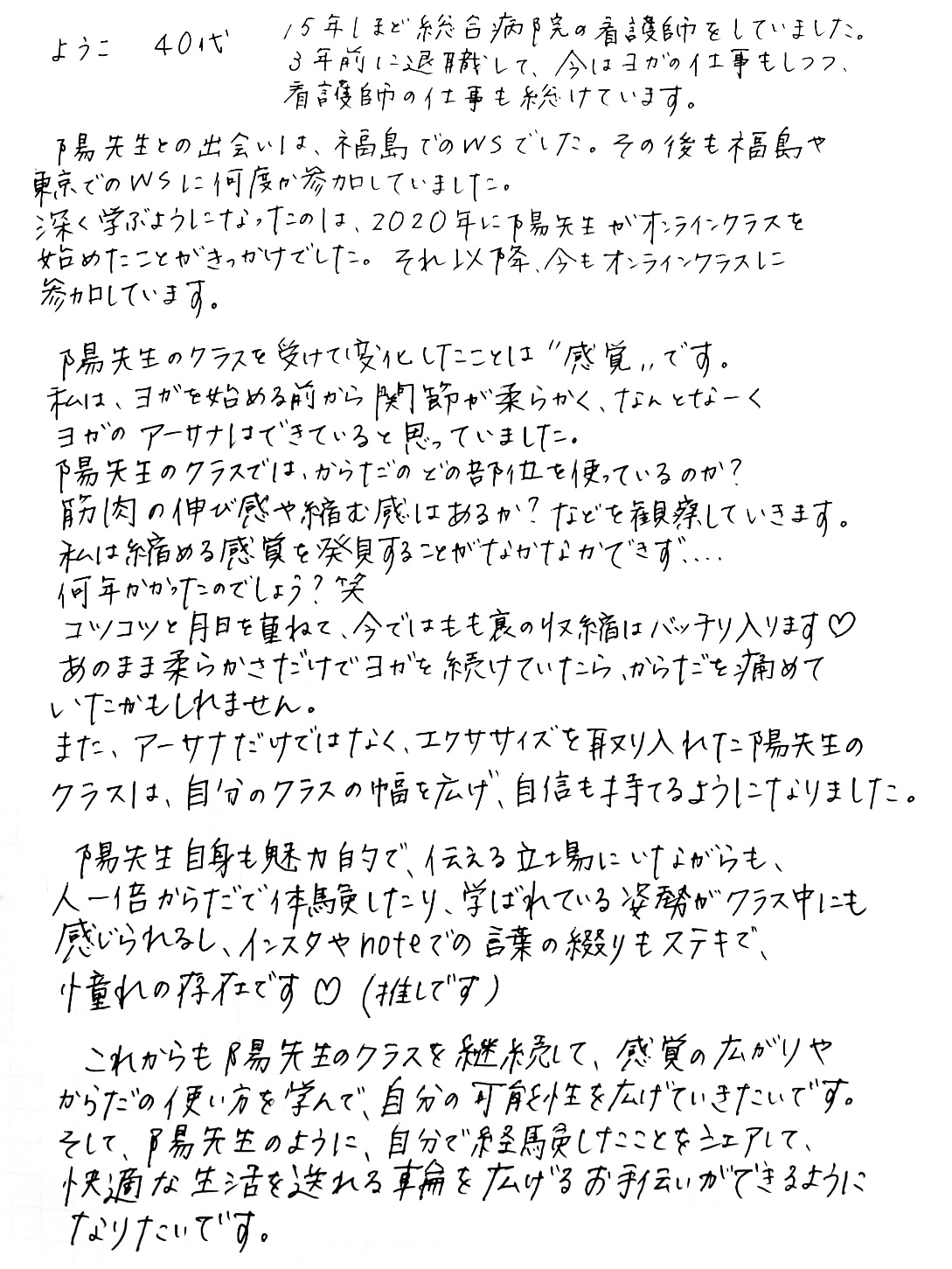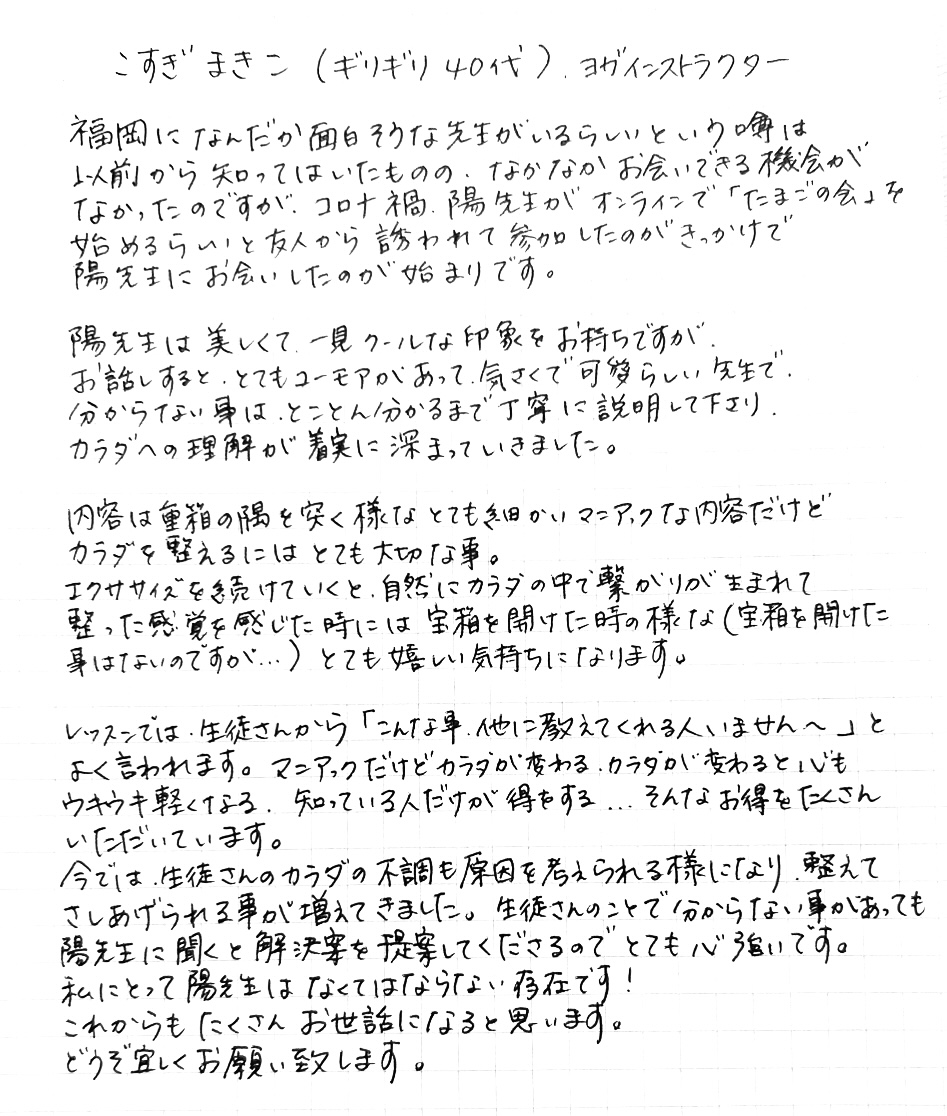Blog
過去からの解放
過去から解放されました
と
あるクライアント様が
言ってくださいました
パーソナルの時は
いつも施術から始めます
その日のコンディションによって
施術と運動の割合は変えますが
お身体を触らせてもらいながら
色んなお話を聞いてます
そんな時
ベットから見える空を見て
「綺麗」とポロッと言葉がこぼれることも
先日
私がある質問をしてから
過去の話題になり
ポツポツと言葉を丁寧に選びながら
ご自身のお話してくださいました
言葉にすることで
気づいていなかった自分に気づく
言葉を毎日使いながらも
自分の深い心の奥を表すことに使うことは
少ないのかもしれない
実際に私のクライアント様も
これまで自分の内側を
こんなふうに言葉にする機会や
話す相手もいなかったと
と話して下さいました
誰しも
自分で自分を癒やす力を持っている
その力が自然と出てくる場を
空の力を借りながら
大切にしていきたいと思います
誰がそう決めた?3歳の自分を取り戻す
以前Ellen Langer 博士の投稿をしましたが、その続きというか、自分のためにも残しておきたいので載せます。
以下は、Mel Robbins のYoutube動画の 「How to Use Your Mind to Heal Your Body With the #1 Harvard Psychologist」から、私が好きなお話の部分を抜粋・編集しています。どうぞ。
私の本のひとつに The Mindful Body(マインドフル・ボディ)というタイトルのものがあります。本を書くときは、まず「どんなタイトルにしよう?」と考えますが、初期の候補のひとつは “Who says so?”(誰がそう言った?) でした。
これは大人のみなさんへのアドバイスでもあります。
ときどき「3歳の自分」を取り戻してほしいのです。「誰がそう決めたの?」「なぜそうなるの?」と問い直してみる。
なぜなら、世の中のあらゆる“当たり前”は、もとは誰かが「こうしよう」と決めた“ひとつの決断”に過ぎないからです。
そして、その“決めた人”とあなたが違えば違うほど、無意識に従わないことがもっと大切になります。
また、世界のすべては不確実です。「1+1は必ず2になる」「馬は肉を食べない」そんなことさえ絶対ではないかもしれない。
だからこそ、あらゆることを“初めて出会うもの”のように扱うのです。
(中略)
私たちは自分を過小評価しすぎているということです。
「できない」と思い込みがちだけれど、多くの場合それは間違いです。多くの人は「専門家でありたい」と思っています。
もし専門家が“常に100%成功する人”を意味するのなら、ちょっと考えてみてください。
小さかった頃、エレベーターのボタンに手が届かなくて、大人に抱き上げてもらいながら押していましたよね。届くまでの過程は全部楽しかった。
でも今、エレベーターに入ってボタンを押せることにワクワクしますか?しないですよね。
つまり、私たちは「完璧にこなせること」からは喜びを感じられなくなる。不完全でありながらも、意識的にやる中にこそ生き生きさがある。
(中略)
私たちは本来、挑戦的なことに惹かれる存在です。
でも「仕事」と「遊び」を間違って理解してきました。一般的には「ワーク」と「ライフ」があって、そこから「ワークライフバランス」が必要だと言われますが、私は違うと思っています。
必要なのは “ワークライフ・インテグレーション(仕事と生活の統合)”。
仕事のときも遊びのときも、同じ自分でいられること。
遊びだって真剣にやることがあるし、仕事でも“自分をそこまで深刻にしない”ことが必要です。私自身は、すべてを“ゲーム”にしてしまいます。
(中略)
なぜマインドフルネスが大切なのか?
理由はたくさんあります。ひとつは、「知っている」と思うと注意を払わなくなるから。
でも世界は常に変化しています。無意識で自動運転のように生きていると、素晴らしいことにも、危険にも気づけません。要するに、“そこにいない”状態です。もし何かをやるなら、その瞬間にちゃんと「そこにいる」こと。そうして初めて活動の恩恵を受けられる。
要はこうです。“機械として生きるか、人として生きるか?”
幸せなとき、遊んでいるとき、興味をかき立てられているとき――そのとき人はマインドフルです。その瞬間、脳の神経は活発に働いている。
簡単な練習として、外を歩くときに新しいものを3つ見つけてみてください。
毎日通る道でも、「あれ?こんなのあった?」と気づくはずです。次に、身近な人、親友やパートナーについて新しいことを3つ見つけてみてください。そうやって“知っているつもりのもの”に新しさを見つけ続けると、やがて「私は思っていたほど分かっていなかったんだ」と気づき、自然と注意が向くようになるのです。
いかがですか?エレン博士のお話は、クリシュナムルティの学校で言われていたことをよく思い出します。
特に「あらゆることを“初めて出会うもの”のように扱う」というところ。
幾つになっても新鮮とイキイキと生きていける。
柔らかな希望に満ち溢れていてとても好きです。
99歳の祖母が教えてくれた、二本目の矢を放たない生き方
日差しから逃げるように、透け感のある大きめのTシャツの袖をヒラヒラさせながら、急足で歩く。日焼け止めを塗ってないのだ。
くうちゃんは、いつものように色んな匂いを嗅ぐのに忙しい。
日差しの奥にはふわふわと、青い空に雲が浮かんでいる。
今日は10月中旬にも関わらず、まるで夏の日。
皮膚も「暑い」と言っているのに、もうすぐ香りを放ちそうな金木犀や、高い木の上から私を眺めている枇杷を見ると、不思議な気分になる。
何かを見れば、そこに感情や思考が生まれる。
そして、その感情や思考の質によって、身体が軽くなったり、重たくなったりする。
思考が身体に与える影響の大きさを、日々感じている。
だからこそ上手に付き合いたいと思う。
最近、Jay Shetty のポッドキャストを聴いていて、「二本の矢」という仏陀の話を知った。
人間の苦しみの構造について説いた、有名な例え話だという。
1本目の矢(第一の矢)=現実の痛み
人間である限り、誰もが避けられない「現実の痛み」や「出来事」が起こる。
• 病気になる
• 人に拒絶される
• 事故に遭う
• 老いる、死ぬ
これらは「第一の矢」。
どんな聖者でも、この矢を避けることはできない。
痛みや悲しみそのものは、誰の人生にも訪れること。
2本目の矢(第二の矢)=心の中で作る苦しみ
ところが、私たちはその出来事に対して、
• 「なんで私がこんな目に…」
• 「あの人のせいだ」
• 「もう二度と幸せになれない」
といった思考・意味づけ・感情反応を加える。
この「思考によって自ら放つ矢」こそが、第二の矢。
「第一の矢は受けるけど、第二の矢は受けない」
ー仏陀
私たちは一矢目ではなく、この二本目の矢によって、苦しみを増幅させている。
この話を聞いてからは、何か起こった時に
「これは何本目の矢なのか?」
「自分で自分に矢を放っていないか?」
と、少し距離を置けるツールをもらった。
99歳の祖母にストレスはあるかと聞いてみた。祖母は「ない」と即答した。
祖母の人生を振り返ると、決してそんなに平坦な人生ではなかったはず。
何が起こっても、抗おうとせず、「そういうものだ」と受け入れて、それ以上考えない。
必要以上に自分を責めたりもしない。
祖母は、第二の矢は放っていないように見える。
本当のところは分からないけれども、
体が丈夫で99歳まで立派に生きているのが、
何よりの証ではなかろうか。
祖母を見習いたい。
まずはビスケット16枚から。笑
今ここにいるということは。
「Be here now(今ここにいなさい)」というのは、
「今ここにいて、そして不快であってもいい」ということなんだ、と。
自分の快・不快や心地よさをコントロールできなくてもいい、ということ。
ただ、その瞬間にやってくるものを受け入れるということです。
Anna Lembke
私は父が亡くなった時に、「心に大きな穴が空いた」と感じました。
小さな穴や、大きな穴が私にはある。
でもその穴を必死に埋めようとせずに、その穴はそのままにして、できることをしようと。
そう感じたのを覚えています。
Podcast番組「The Daily of A CEO」で、アメリカの精神科医のAnna Lembke博士がドーパミンについてお話しされていました。その中で出てきたご自身の経験談や考え方を聞いて、心が晴れる話ではないのに、スーッと優しい風が心に流れました。
初盆を迎えている人もいるかもしれない。
ポジティブになんか考えられない人もいるかもしれない。
そういう方の何かのきっかけになればと思い、シェアさせて頂きます。
Dopamine Expert: Doing This Once A Day Fixes Your Dopamine! What Alcohol Is Doing To Your Brain!
たぶん問題の一部は、私たちの生活が今ではほとんど「報酬」を中心に組み立てられていることだと思います。
ほとんどすべての行動が、「その先にある気持ちいい瞬間」を前提にしていて、そのせいで私たちは“過程”を逃してしまっている。
私たちの心は未来の報酬へと投影されてしまっていて、今この瞬間に本当にいることができないんです。
「Be here now(今ここにいなさい)」というのは、
「今ここにいて、そして不快であってもいい」ということなんだ、と。
自分の快・不快や心地よさをコントロールできなくてもいい、ということ。
ただ、その瞬間にやってくるものを受け入れるということです。
これは大きな転換だと思います。
つまり、私はもう自分の経験をコントロールしようとしない。
不幸せだったり、落ち着かなかったり、不快であっても、それから逃げずに、ただそれを正面から受け止めて抱きしめる。
そしてこれは多分、普遍的なことだと思います。
さらに大事なのは、報酬を期待しないこと。
そうすることで私は今にいられるんです。
「この先にいいことが待っている」と待ち構えるのではなく、
「この後には何もいいことはないかもしれない、何も来ない」と自分に言い聞かせる。
これがすべてなんだ、と。
そして、「もし今が特別に良くなくても、それでいい」と思える。
不幸せでも、落ち着かなくても、不安でも、それを受け入れられる。
そうすると不思議なことが起こります。
急に不安が薄れて、今この瞬間に存在できるようになる。
そしてそこには喜びさえ見えてくる。
現代文化が煽っているのは、「私たちは常に幸せであるべき」という期待です。
人生をきちんと整えて、努力して、正しい方向を目指せば、「人生は素晴らしい」となるはずだ、という考え。
でも私はもうそうは信じません。
仏陀が言ったように、「人生は苦」であり、根本的には、生きていることは不快で、絶え間ない落ち着かなさと不快感の状態だと思います。
本当に正直に自分を見つめ、感じてみると、急にその一部から解放されるんです。
――あなたは人生を通して不安を感じてきたとおっしゃいましたが、それを理解し、自分をよりよく理解するきっかけとなった出来事とは何ですか?
私にとって大きな転機は…私たちは子どもを亡くしたことでした。
そして、その直後は、なんとかその経験を「なかったこと」にしようと必死でした。
十分な心理療法を受けたり、とにかく必要なことを全部やって、この痛みを感じなくしようとしたんです。
でも、あるときふと気づいたんです。
「ああ、この痛みは一生消えないんだ」と。
その瞬間、逆に少しだけ痛みから解放されたような感覚がありました。
私にとって、それは本当に大きな気づきの窓でした。
――つまり、それは「受け入れ」なんですね。
そうです。そして、私が依存症の患者さんを治療することが好きな理由の一つもそこにあります。
彼らが「どん底」に落ちる瞬間、つまり、自分の行動をなんとかコントロールして人生を良くしようとするほど、かえって状況を悪化させてしまう、あの瞬間に、私はとても共感できるんです。
私もまったく同じような経験をしました。
そして、「ああ、私はこの痛みから逃げられないんだ」ということを受け入れたとき、やっと少しだけ救いのようなものが見え始めたんです。
――痛みから逃げられない…。人間って、痛みから逃げようとする性質が自然に備わっていますよね。
そう、それが皮肉なんです。私たちは本能的に快楽を求め、痛みを避けようとします。
でも実は、その行動こそが、私たちが本当に望む場所へたどり着けない原因になってしまうんです。
ーーそして現代は、痛みから逃れる方法があまりにも簡単に手に入る世界になっています。
かつては「ライオンに追われている」ような差し迫った状況でしか発動しなかった本能が、今では例えば「嫌なメールを受け取った」というだけでも発動します。
そして私はブラウザのタブを開いて延々とSNSをスクロールしたり、動画を見たり、ゲームをしたり、ポルノを見たり…いくらでも気をそらす方法がある。
まさにそうですね。私たちには、自分の苦しみや内面から意識をそらす方法が無数にあります。
――では今、あなたはその悲しみや痛みとどのように向き合っていますか?
そうですね…今では、その経験は私の人生において大きな「贈り物」になったと感じています。
それによって、私の人生は深く形作られ、そしてあの経験から学んだことは、他のどんな方法でも学べなかっただろうと思います。
ふさわしい人がいるのではなく、ふさわしい人になっていく 【アメリカ留学記】
言葉に救われた経験はあるだろうか。
“God doesn’t choose the qualified, God qualifies the chosen.”
Papa Peter Rhodes.
「神は資格のある者を選ぶのではなく、選ばれた者に資格を与える」
神(あるいは運命や宇宙)が人を選ぶ際、最初から完璧な能力や資質を持っている人を選ぶのではなく、まず人を選び、その後でその人が使命を果たせるように必要な資質や能力を授ける。
最初から「ふさわしい」と思われる人が選ばれるのではなく、選ばれた人が後からその役割にふさわしい者になっていく。
Darren Rhodesのお父様の言葉
これはDarren Rhodesをスタジオに呼んで、yogahour のティーチャートレーニングを開催する事が決まり、私が通訳できるか不安に思っていた時にダレンがくれた言葉だ。この言葉に何度勇気づけられたことか。
Darren Rhodesは、1999年からアリゾナ州ツーソン市にあるYogaOasisスタジオのディレクターを務め、またYogahourという独自のスタイルのヨガクラスを考案した。Yogagloの講師やポスターのモデルを務めたり、The Yoga Resource Practice Manualという360ポーズについての本を書いている。

最初にダレンのクラスを受けたのは、アメリカのヨガのオンラインサイト『Yogaglo』だった。「なんて嘘のない人だろう」というのが最初に受けた印象で、あっという間に虜になりダレンのクラスだけを毎日練習するようになった。
クラスの内容も通常のクラスの流れとは違いユニークなものだったが、何よりクラスの前の話にいつも心が動かされた。ダレンの言葉は決して人にこういう風に考えたらいいとか、そういう押し付けではなくて、自分の小ささも含めた実体験を話してくれていて、それが優しく心に染み込んだ。
毎朝練習していると、夢にまでダレンが出てくるようになったので、もうこれは会いに行くしかないと思い、トレーニングに行くことにした。
とりあえずダレンに会えればそれでいいと思っていたので、ホームページに記載されていたトレーニングに申し込んだ。それがダレンたちにとっても最初のヨガアワーのトレーニングだった。

トレーニング会場は、フィラデルフィアにあるMaha Yoga Studio。
前日にフィラデルフィアに着き時間があったので、スタジオにゼンニャ(※日本でワークショップを受けたことがあり、ヨガを指導する上で大きな影響を与えてくれた女性)のクラスを受けに行ったら、なんとダレンもそこに来て、私の真向かいにマットをひいた。あまりにもドラマチックで、今ならドラマの主人公になれると思った。終始ドキドキしながらクラスを受け、クラス後にダレンに挨拶に行ったら、とても驚いた顔をして、「YOって男だと思っていた!」と。え?
資格がもらえるわけでもないトレーニングに、わざわざ日本から受けにくるなんてどんな男の人だろうと思っていたらしい。
ダレンとゼンニャとよそ見してしまった私
トレーニング当日、ワクワクした気持ちと、イギリス留学時に最初は英語が話せず馴染めなかったトラウマがぴょこぴょこ出ながら、会場に向かった。しかしそのトラウマは会場に着いた瞬間に消えた。参加者の人達が、わざわざ日本からやってきたということで、とても暖かく向かい入れてくれたのだ。
トレーニングが始まり、ダレンがヨガアワーがどのようにして始まったのか、ヨガアワーとはどういうシステムなのかを話してくれた時に、「これは私のための作られたトレーニングか?」と思うくらい、「そうそう!こういう事が学びたかった」と、頭が取れそうなくらい頷きながら話を聞いたのを覚えている。
しかし実際に指導をし合う時間になった時に、「あれ?私英語で教えたことなんてないけど?」と、英語で教えれない事にようやく気づいた。
喜びが脇汗に変わった。全然指導できない。
スムーズに行かず、ペアになった人に迷惑をかけている事にハラハラが止まらない。
1日目が終わった時は、水をかぶったアンパンマンみたいに疲れ果てていた。こんなに話せないのはダメだと、帰ってから、そして翌朝も早く起きて英語で教える練習をした。
その時のブログに下記のように書いていた。
今まで培ってきたものを、全てゼロに戻している気がします。
そういう事が今の私には必要だったんでしょうね。

このトレーニングが終わった時に、「陽が来てくれたのが、このトレーニングのハイライト。日本に教えに行くよ」とダレンが言ってくれた。
そこから私のヨガアワーの道がスタートした。
ダレンが私を選んでくれ、200時間のヨガアワーのティーチャートレーニングをスタジオで開催するために必要な資質を能力を授けてくれたおかげで、素晴らしい人たちに出会うことが出来た。この経験が間違いなく私の人生のハイライトの1つである。

ダレンのスタジオの看板にはYOと書いてある。
エモい。

ヨガでO脚が改善しなかった私が、今は改善できると思うわけ
数年前までは、ヨガをしているというと何でも全てが整っている人という印象を持たれていました。心も体も。
そんなわけがない。私に関しては。
インドで初めてヨガに出会って、インドと日本を行き来しながら2年間近くアイアンガーヨガを学び、帰国後はアヌサラヨガに出会って、インド哲学にも触れて、「人としてどうありたいか、ヨガを伝えていくあり方」を深く学びました。
その当時は、1日2時間ほど毎日練習していて、ポーズの熟練度はどんどん上がっていきました。しかし私の頑固なO脚は改善されず、「なぜ色々できることは増えていくのに、O脚は改善されないのだろう」と思っていました。
ヨガを始めた理由は「O脚をなおしたいから」とかではなかったのですが、「いつかやっていたら治るのかな」と思っていたら、その「いつか」がなかなか来ず。
そんな時Facebookで知人のピラティスインストラクターの方が『re・Frame Conditioning Academy』の石井定厚先生の「美姿勢美脚セミナー」を告知されていたので行ってみることに。
なんだ、そういう事だったのか!と目から鱗の内容で、セミナーが終わったあとにすぐに石井先生にメッセージをして、パーソナルの予約を取りました。それからというものヨガの学びだけでなく、様々な運動療法や徒手療法のセミナーに参加する日々が始まり、今でも継続して学んでいます。
最近の写真はちょっと頑張って寄せましたが、以前は寄せることすら出来ませんでした。

Processed with MOLDIV
色々やってきましたが、体がとても変わり出したと感じ始めたのは、体幹が入っている時とそうでない時の違いを、はっきりと感じられるようになった頃です。
呼吸のエクササイズや、施術で体幹を働きやすくしてもらった時の、全然力を入れようとしてないのに体が安定している感覚は、今まで自分で体幹トレーニングをしていた時の感覚とは全く違いました。不必要な力が抜けるようになって、体のつながりを感じられるようになりました。
まだまだ改善点の多い体ですが、下半身に問題があるからと股関節のトレーニングばかりするよりは、全ての関節の動きを適切にして、
ようにした方が良いなぁと感じる今日この頃。
ヨガでO脚が改善できなかったのは、私が持っていた運動のイメージが、機能的な動きからズレていたからというのが大きいです。なのでヨガでも、機能的な動きとその人が持っている運動イメージの擦り合わせを行い、その人に合ったヨガのアーサナを選ぶことで、O脚を改善することは可能だと思います。
この骨格に生まれてよかったとは思いませんが、同じ悩みを持ったクライアントさんに寄り添えることは多々あります。
1年くらい前からパーソナルに通われるようになったクライアント様は、人工股関節置換術をされていて、整形外科の先生にもO脚を指摘されていらっしゃいましたが、最近は「脚がまっすぐになってきたね」と褒められるそうです。
O脚であることが、若い頃は審美的な問題でも、年齢が高くなってくると変形性膝関節症の問題に。そしてひどくなれば手術。なるべく早い段階で適切なトレーニングをして骨の変形が起こらないようにできたら良いですね。
そして今回この投稿を書きながら感じたことは、自分の体に責任感を持つこと。投稿を書き始めた時から身が引き締まって、内転筋と大臀筋下部の筋収縮がとてもよく入るようになってきました!笑
意志の力が体に大きく働きかけることを実感した1週間です。
私は心も体も整っているわけではないです。
でも年を重ねても若い頃よりも動けるし、今の自分の方が好き。
ヨガに出会えて良かった。
あなたはギバー?それともテイカー?違いがわかるたった1つの質問。
あなたは『ギバー』か、それとも『テイカー』か。
Your greatness is not what you have, but what you give.
人の偉大さは何を持っているかではなく、何を差し出すか。
ギバーとは、「どうすれば人の役に立てるか」を考える思考傾向があり、長期的な関係構築を重視する人。
一方テイカーとは、「自分にとって何が得られるか」を考える思考傾向があり、短期的な利益を重視しがちな人。
自分はどちらだろう。
ギバーのつもりでいても、テイカーになっているのかもしれない。
どちら側に立っているのか、Jenna Zoeの『Align with Jenna Zoe』というPodcast番組で、David Ghiyam が分かりやすい表現を話されていた。
たとえば、このポットキャストの予定を、Jennaがキャンセルしたら、私はどう感じるか。
もし寂しく感じたとしたら、それは自分のイメージを高めるためなどに、このポットキャストを利用している『テイカー』ということになる。
なので私はいつも仕事のミーティングの予定を見て、もしこれらのミーティングがキャンセルされたとしても、ミーティングがあった時と同じように、楽しく過ごせるかを自分自身に問うようにしている。
もし、その答えが「Yes」なら、そのミーティングに『ギバー』として参加していることになる。
楽しみな予定があったらとても嬉しいけど、なくなったとしても自分で楽しく過ごせるかどうか。
それが『ギバー』というのが、とても分かりやすい表現だと思った。
これは仕事だけでなく、人間関係でも同じことが言えるそう。
これを聞いてから、「あ!あの時は私はテイカーになっていたなぁ」と、ハッとさせられ、恥ずかしささえ感じる。
状況によって私たちは『ギバー』にも『テイカー』にもなりうる。
だからこそ何ごとも気づくことから。
今日のあなたはどちらですか。
書家の娘として育つこと
「ようちゃんは墨のにおいがする」
と幼い頃よく友達に言われていて、私には自分が墨のにおいがする事が分かりませんでした。
私は書家の家に生まれました。
祖父が「福岡書芸院」という名の会を作り、父へと、そして祖父と父が亡き今は姉が継いでいます。
書家の家だというと、厳格な家に育ったイメージを持たれたり、「家でお父さんは着物を着ているの?」としばしば聞かれる事もありました。
我が家に関しては全くそういうことはなくて、父に「書を継ぎなさい」など言われた事もありませんでした。洋服に関しても、父は家でもいつでもお出かけできる格好で過ごすことをモットーとしていたので、若い頃は白かチェックのシャツにデニム、晩年も冬には黒やネイビーのカシミアのニットにコーデュロイのパンツという感じでした。私の姉は墨がつくからと、黒い服をよく選んでいます。
書があることが当たり前で、書を書くことに抵抗がないというのが、もしかしたら特有の感覚なのかもしれません。
書は下手だから書けないと言われることもよくあるのですが、
我が家のリビングには
「絵でも書でも上手に書こうだなんてとんでもないことだ」
という熊谷守一の言葉を彫った父の版画が飾ってあり、毎日それを見て育ったので、書に対する初期設定がそもそも違ったように思います。
以前インドで緑化活動をしている友人に仕事についての話を聞いた時にとても感銘を受け、一つのことに長く時間をかけてきた人達に話を聞いてみたいと思い、父にも書について聞いた事がありました。
1:みんなに褒められる一般的に上手と言われる字を書けるようになる秘訣は?
先生の言うことを聞いて、お手本を真似て、そっくりに書けるようになるまでたくさん書くこと。
2:自分の字で、自分の作品を作る秘訣は?
筆で日記を書いたり、思いついたことを書き留める。(鉛筆でもよい)。
誰かの言葉でなく、自分の言葉で書くことが、自分の作品になる。
3:豊かな字を書く秘訣は?
豊かな書に出会うこと。
豊かな書をたくさん見て、たくさん書く。
たくさんとはどのくらいかというと、父は大学卒業してから30歳になるまで、毎日夜中から明け方まで臨書していたそうです。臨書とは古典の原本をしっかり見て、線を観察しながら書く事です。何を書くかによって枚数は変わるけれども、1日半紙に30〜60枚、1年間で1万枚以上。30歳になった頃に「もう人の真似をするのはやめよう」と思い、臨書するのをやめたそうです。父が大好きだった坂口恭平さんも常に質より量と言われていますが、この量をこなせる人というのが一握りではないでしょうか。
祖父も父も亡くなる直前まで現役で仕事をしていましたし、毎日本を読み、書の探求を続けていました。私も「なぜそんなにずっと体の勉強を続けられるのか」と聞かれたり、「とても努力家だ」と言われることがあるのですが、自分としてはあまり努力している感覚はなく、父の学び続ける姿を見て育ったのでそれが当たり前だからなのかもしれません。
自分が墨のにおいがすることが分からないのと同じくらい、私という人間は隅々まで父の影響を受けていたようです。でも嫌いじゃない。
おじいちゃん、おとうさん、そして姉よ、継いでくれてありがとう。
自己肯定感が見当たらない時は、草取りをしたら良いと思う
ガサガサガサガサ
朝を知らせる鳥の声と、仕事へと急ぐ車の音と、鍬の音が交差する。
私の頭の中では「ブルドーザー陽」という言葉がマントラのようにリピートしている。
昨年の夏に、ずっと長年庭の手入れをしていた祖母が熱中症になった。祖母は今年でなんと99歳になるスーパーおばあちゃん。ビスケットが身体にとても良いと思っていて、お昼ごはんはビスケット16枚。健康ってなんだろうと祖母を見ているといつも思う。
祖母が庭の世話が出来なくなり、代わりに草取りを始めた。夏の間は早起きしてやっていたが、冬になると空が真っ暗で出来なくなった。でも冬は草は生えないと聞いていたので、まぁいいかと思っていたら、冬にもちゃんと草は生えるではないか。特にクローバー。多すぎて四つ葉のクローバーを探す気にさえならない。
日中は何かと予定が入ってしまうので、「どんどん育ってますよ」と声をかけてくる草に「また今度」と言いながら日々過ごしていたら、春の訪れと共に庭が大変なことになってしまっていた。
日が昇るのが早くなり、また朝の草取りを再開した。庭の場所によって草取りの勝手が違う。土だけのところは、立って鎌でガサガサできるのだが、石が敷き詰めてあるところがなんとも難しい。
昨年の夏ガーデニング用の椅子を買い、それに座って草取りをしていたが、やはり長時間座っていると腰が痛くなってくる。
そこで先日、四つ這いでやったら良いのではないかと思いつき、段ボールを膝の下に敷いてやってみたら、なんと素晴らしいこと。
不安定な場所に手や膝をついて体を支えるので、良い体幹のトレーニングにもなるし、視野も変わり、土の匂いなどもより強く感じ、たくさんの感覚入力が入る。座ってやるよりも断然スピードが早いし、1時間やっても疲れず、永遠に出来そうな気さえする。姉が買ってきた鍬がまた素晴らしく、まるで自分がブルドーザーになったような気持ちにさせてくれて、どんどん作業が進む。
ただ四つ這いのトレーニングを1時間もするのは、つまらないのでやってみたくもないけど、草をとって庭を綺麗にするという目的があれば安易に出来てしまう。
これが目標指向型運動というものであろう。
体のことを勉強していると、様々な日常の動作がどのように自分にとって良い影響を与えているのか、もしくはどうやったら良い影響に変えることができるのかが分かり、つまらない動作も面白くなるところがとても良い。
そして何より草取りは、成功体験しかない。誰でもできる。絶対やった分だけ成果が瞬時に出る。
すごく綺麗になった庭を見て、自然と「がんばったね、私」と労う。
日焼けと、ヤケーヌによる肌への摩擦、そしてこれからは蚊による攻撃が待っているが、自己肯定感がお散歩してしまった時には、とても効果的ではなかろうか。
何年も前は、毎朝起きてすぐヨガの練習を2時間近くしていた。2時間も朝練習できるとは、私はなんて幸せ者なのか、と毎日思っていた。
今は草取りをしていてそう思う。
すごい楽しい事だけが毎日起こっているわけではないけど、草取りをする余裕があるというのは、家族が元気で平穏だからできること。
小さな幸せを愛でる。
きっとそれが健康の秘訣、16枚のビスケットのように。
こうあるべきを手放したら見えてくる世界
ハーバード大学の心理学者であり、「マインドフルネスの母」と呼ばれているエレン・ランガー博士のお話が好きです。
日本語版の本も多数出版されていますが、読んだことはありません。
Podcastでたまたまエレン博士のことを知って、それから色々と聞いています。
ChatGPTにマインドフルネスについて尋ねてみると、
・「マインドフルネスとは、今この瞬間の体験に、評価や判断を加えず、意図的に注意を向けること。」
・実践方法は、「瞑想と日常の気づき」
との返事をもらいました。
瞑想が代表的な方法とも言われているのですが、エレン博士によると、
・瞑想は、世界から自分を切り離して、1日2回、20分間静かに座るという「練習」で、よりマインドフルになるための手段。
・マインドフルネスは、「生き方」で、「不確かさの力(the power of uncertainty)」を深く、でも軽やかに理解することから生まれるとのこと。でした。
以下は、ランガー博士が出演されていたポッドキャストから抜粋しました。
「不確かさの中にある力を理解し、今この瞬間に気づいて生きること」。
私たちは幼いころから、「これは正しい」「こうあるべき」といった絶対的なルールを教え込まれてきました。
でも、世界は常に変化していて、視点が変われば真実も変わります。
私たちは本当には“知る”ことができない。その「わからなさ」を受け入れることが、マインドフルに生きる出発点なのです。
何年も前に私にとって非常に重要な出来事ありました。
ある男性に会い、「僕の馬を見ていてくれないか。馬にホットドッグを買ってきたいから」と頼んできました。
馬はホットドッグを食べませんよね。ニンジンを食べます。穀物を食べます。肉は食べません。
しかし彼はホットドッグを持って戻ってきて、馬がそれを食べたんです。
その時、私が知っていると思っていた全てのことが間違っている可能性があると気づきました。
そして科学についても考えました。
多くの人は誤解していますが、科学が示しているのは「確率」であって「絶対」ではないんです。
たとえば「馬は肉を食べない」という命題。
科学的に実験すれば、「この種類の馬」「この体重」「この時間に」「この量のエサを食べたあと」など、細かい条件のもとでは「たいていの馬は肉を食べない」という結果になるでしょう。
つまり「馬は肉を食べない」というのは、正確にはその複雑な条件を省略した「要約」なんです。
私たちの人生もそれと同じです。
子どもの頃に無意識に刷り込まれた考えが、大人になっても行動を支配している。
多くの人は、そういう無意識の影響に気づいていません。
50年近く研究してきて、私は確信しています。
ほとんどの人は、ほとんどの時間を「マインドレス(無意識)」に過ごしている。
しかも、その状態に気づいていないんです。
「そこにいない」けれど、「いないことに気づいていない」状態。
たとえば誰かに「馬は肉を食べる?」と聞かれたら、反射的に「いいえ、馬は肉を食べません」と答えるでしょう。
でもそれは、少なくともある文脈では「間違い」なんです。
では、マインドフルに生きるとはどういうことか?
それは、「今この瞬間に関わること」。
ロボットのように自動反応せず、感じ、観察し、気づいていること。
ワクワクしたり、穏やかであったり――そんな人間らしい感情を味わえているとき、私たちはすでにマインドフルな状態にあります。
マインドフルネスとは、自分の人生の主導権を取り戻すこと。
常識や他人に委ねてきた人生を、自分自身の手に取り戻す――
それこそが、「マインドフルに生きる」ということなのです。
いかがでしょうか?
ランガー博士は現在78歳ですが、全くストレスがないとおっしゃっていました。
それは物事は常に不確かであるということを、本当に理解しているからだそうです。
自分で自分のことを決めつけさえしなければ、私たちはきっとどんな事も可能なのだなと思いました。
私も本がスイスイ読めるようになることも、きっと。